「LPICってよく聞くけれど、どんな資格なんだろう?」「IT未経験でも取れるの?」
そう感じている方も多いのではないでしょうか。
結論から言うと、LPICはLinuxの知識とスキルを客観的に証明できる、インフラエンジニア転職に強い国際資格です。
Linuxサーバーの構築・運用スキルを学ぶことで、クラウドやセキュリティ分野にもつながる土台を作ることができます。
この記事では、LPICの基礎からレベル別の違い、試験内容、勉強法、転職への活かし方までを体系的に解説します。
これからIT業界に挑戦したい方や、未経験からエンジニア転職を目指す方は、この記事を読めばLPICの全体像をつかめるはずです。
- LPICとは?初心者でもわかる3つの基本ポイント
- LPICのレベル別違いを理解する3ステップ(LPIC-1・LPIC-2・LPIC-3)
- LPIC試験の申し込みと受験の流れを押さえる3つの手順
- LPICの試験内容・勉強時間・合格率の3つの目安
- LPIC Level1の過去問から学ぶ3つの対策ポイント
- LPIC取得でキャリアが広がる3つの理由
- LPICとLinuC・Linux Essentialsを比較する3つの観点
- LPIC廃止の噂を正しく理解する3つの視点
- LPICの勉強法を成功させる3つのコツ(独学・スクール別)
- LPICの有効期限と更新方法を理解する3つのポイント
- LPIC取得後に伸ばすべき3つのスキルと次の資格
- まとめ
LPICとは?初心者でもわかる3つの基本ポイント
「LPICって聞いたことはあるけど、どんな資格なのかよく分からない…」と思っている方も多いでしょう。
でも安心してください。この記事を読めば、LPICの概要からメリットまでを簡単に理解できます。
LPICの概要と認定団体(LPI)について
LPIC(Linux Professional Institute Certification)は、カナダの非営利団体「LPI(Linux Professional Institute)」が運営する、世界的に認められたLinux技術者認定資格です。
ベンダーニュートラル資格(特定企業に依存しない)であるため、Red HatやUbuntuなど、どのLinuxディストリビューションにも対応しています。
LPIは1999年に設立され、世界180か国以上で試験が実施されています。
LPICは、グローバルに通用するLinuxスキルを証明できる資格として、多くの企業が採用基準の一つにしています。
LPICが評価される理由と特徴
LPICは、Linuxシステムの構築・運用・管理に必要な実践スキルを体系的に問う試験です。
特定の製品知識に偏らず、オープンソース環境で汎用的に通用する技術が学べるのが特徴です。
また、LPICは世界共通の試験体系を採用しており、どの国で受験しても同一基準で評価される点が信頼性の高さにつながっています。
ITインフラやサーバー運用を行うエンジニアにとって、LPICはスキル証明として非常に有効です。
LPICを取得するメリット
LPICを取得することで、Linuxに関する理解が一気に深まり、業務効率やトラブル対応力が格段に上がります。
特に未経験者にとっては、「Linuxを触れる」だけでなく、「理解して扱える」状態にステップアップできることが最大の利点です。
また、採用担当者からの信頼性も高く、「Linux運用を任せられる人材」としての証明になります。
転職市場でも評価が高く、ITインフラエンジニアへの転職を目指す人にとって非常に有利な資格です。
LPICのレベル別違いを理解する3ステップ(LPIC-1・LPIC-2・LPIC-3)
「LPICっていくつかレベルがあるけど、どこから受ければいいの?」と迷う方も多いでしょう。
しかし心配はいりません。この記事を読めば、各レベルの違いと学ぶ順序が明確になります。
LPIC-1:Linux基礎を証明する最初のステップ
LPIC-1は、Linuxの基本操作と管理を扱うエントリーレベルの資格です。
コマンド操作、ユーザー管理、ファイルシステム、シェルスクリプトなど、日常的な運用業務に必要な知識を問われます。
試験は「101試験」と「102試験」の2科目構成で、両方に合格することで認定されます。
IT未経験からインフラエンジニアを目指す人は、このLPIC-1が最初の目標になります。
LPIC-2:サーバー構築やネットワーク設定に関する中級資格
LPIC-2は、LPIC-1の知識を前提とした実践的なサーバー構築スキルを問う資格です。
DNS、DHCP、Webサーバー、メールサーバーなどの構築・設定に加え、トラブルシューティング能力も評価されます。
このレベルを取得すると、社内インフラ構築や運用設計に携われる中級エンジニアとしての評価を得られます。
試験は「201試験」「202試験」の2科目です。
LPIC-3:上級エンジニア向けの専門資格
LPIC-3は、Linuxを専門的に扱うエンジニアのための最上位資格です。
試験分野は複数あり、「セキュリティ」「仮想化」「ハイアベイラビリティ(高可用性)」など、専門分野ごとに試験が分かれています。
大手企業やSIerでは、サーバー設計・運用リーダーを任される際に評価される資格です。
高度な知識が求められるため、LPIC-2取得後に一定の実務経験を積んでから挑戦するのが一般的です。
LPIC試験の申し込みと受験の流れを押さえる3つの手順
「LPICを受けてみたいけど、どうやって申し込むの?」という方も多いのではないでしょうか。
安心してください。LPICは手順を理解すれば、誰でも簡単に申し込みから受験まで進められます。
試験の申し込みサイトと手順
LPICの試験は、ピアソンVUE(Pearson VUE)という公式試験サイトから申し込むことができます。
手順は以下の通りです:
- ピアソンVUE公式サイトにアクセス
- アカウントを作成し、「Linux Professional Institute(LPI)」を選択
- 受験する試験番号(例:101-500、102-500)を選び、希望日時と会場を指定
支払いはクレジットカードやバウチャーチケットで行えます。
受験方式(オンライン・テストセンター)
LPIC試験は、全国のテストセンター受験とオンライン受験の両方に対応しています。
オンライン試験の場合は、自宅のPCとウェブカメラで受験可能ですが、通信環境や本人確認の手順に注意が必要です。
一方、テストセンター受験では、安定した環境で受験できるため初めての方におすすめです。
受験当日の注意点
受験当日は、本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)を必ず持参してください。
試験時間は90分で、途中退室はできません。
リラックスして挑めるよう、前日は十分な睡眠を取り、試験範囲の要点だけを復習すると良いでしょう。
LPICの試験内容・勉強時間・合格率の3つの目安
「LPICの試験ってどんな内容?」「どのくらい勉強すれば合格できるの?」
そんな疑問を持つ方のために、ここでは試験の構成や学習時間の目安をわかりやすく整理します。
LPIC-1の出題範囲と試験構成
LPIC-1は、Linuxシステムの基本操作と管理を中心に出題されます。
試験は「101試験」と「102試験」の2つで構成されており、どちらも選択式と記述式の混合です。
出題範囲の例:
- システムアーキテクチャ
- GNUとUnixコマンド
- デバイス・ファイルシステム管理
- ユーザー管理と権限設定
- シェルスクリプトの基礎
Linuxの構造を理解しているかだけでなく、「どのように操作すればよいか」が問われる実践的な内容です。
試験時間・合格点・受験費用の概要
試験時間はそれぞれ90分で、出題数は約60問。
合格点は500点満点中約500×0.5=250点前後(※正確な点数は非公開)とされています。
受験費用は1科目あたり税込16,500円前後が目安です。(最新情報は必ず公式でご確認ください)
また、試験は随時開催されており、受験者の都合に合わせて日程を選べます。
独学合格に必要な勉強時間の目安
未経験者が独学でLPIC-1に合格するためには、おおよそ150〜200時間の学習時間が必要です。
1日2時間の勉強ペースなら、約3か月での合格が現実的なラインです。
効率的に学ぶためには、以下の方法が効果的です:
- Ping-tなどの問題演習サイトで繰り返し解く
- 模擬試験で出題傾向を把握
- Linux環境を実際に構築し、手を動かして確認する
LPIC Level1の過去問から学ぶ3つの対策ポイント
「どんな問題が出るのか知りたい」「効率的に勉強したい」
そんな方にとって、過去問の活用は最も効果的な学習方法です。
ここでは、LPIC Level1(LPIC-1)の過去問を使った学習法を3つの視点で解説します。
過去問の入手先と注意点
LPICは過去問が公式に公開されていません。
そのため、Ping-tやUdemyなどのオンライン学習サイトを活用するのが一般的です。
特にPing-tは、出題傾向に近い問題を多数掲載しており、受験者の実体験に基づいた解説が充実しています。
ただし、古い問題集や非公式サイトでは出題範囲が改訂前の内容になっている場合があるため、
「バージョン500以降対応」などの最新版教材を選ぶことが重要です。
出題傾向の分析と学習ポイント
LPIC-1では、コマンドの正確な使い方や設定ファイルの位置を問う問題が多く出題されます。
つまり、「なんとなく理解している」だけではなく、実際に打ち込んで動かして覚えることが必須です。
出題傾向としては以下のような分野が頻出です:
- ファイル操作(cp、mv、grep、find など)
- パッケージ管理(dpkg、rpm、apt、yum)
- システム起動とログ管理
特に「実務を意識した問題」が多いため、手元に仮想環境を構築して練習することが合格への近道です。
効率的な復習方法
学んだ内容を定着させるには、間隔をあけて繰り返す「スパイラル復習法」が効果的です。
1週間以内に同じ範囲を2回、1か月後にもう1度見直すことで、長期記憶に残りやすくなります。
また、問題を解くだけでなく、「なぜその選択肢が間違っているのか」を理解することも重要です。
理解ベースの学習は、LPIC-2以降にも必ず役立ちます。
LPIC取得でキャリアが広がる3つの理由
「LPICを取ると本当に転職に有利なの?」「キャリアアップにどうつながるの?」
そう思う方も多いはずです。ここでは、LPICがなぜキャリア形成に効果的なのかを3つの視点から解説します。
未経験からインフラエンジニアへステップアップ
LPICは、Linuxの運用スキルを体系的に学べる資格です。
未経験者でも、Linuxの基本操作やサーバー構築を理解することで、インフラエンジニアとしての第一歩を踏み出せます。
特にLPIC-1を持っていることで、採用担当者から「基礎が身についている」と判断されやすく、実務経験が浅い人でも採用対象になります。
これは、学歴や経歴に関係なく、スキルで評価されるチャンスを広げる大きなメリットです。
LPICが評価される職種と業界
LPICは、Linuxサーバーを扱う多くの企業で高く評価されています。
具体的には以下のような職種・業界で有利です:
- サーバー運用・保守エンジニア
- クラウドインフラエンジニア(AWS、GCPなど)
- データセンター運用担当
- 社内SE(システム管理者)
また、AWSやAzureなどのクラウド環境もLinuxベースで動作しているため、クラウド時代の基礎スキルとしての重要性も増しています。
LPICが転職活動で有利になる理由
LPICは、資格そのものがスキル証明になるだけでなく、学習意欲と技術理解を示す指標にもなります。
特に未経験者が応募する場合、「独学でLPICを取得した」という実績は、採用担当に強い印象を与えます。
さらに、求人票で「Linux経験者歓迎」「LPIC保有者優遇」と明記されている企業も増加中です。
これは、LPICが実務スキルと直結していることの証明でもあります。
広告導線例
IT転職を目指す方には、「テックゲート転職」がおすすめです。
エンジニア未経験OKの求人豊富で、キャリア相談も無料で受けられます。
LPICとLinuC・Linux Essentialsを比較する3つの観点
「LPICとLinuCって何が違うの?」「どっちを取ればいいの?」
Linux資格を調べると必ず出てくるこの疑問を、ここでは3つの観点から整理して解説します。
LPICとLinuCの違い(国際資格と国内資格)
LPICは、カナダのLPI(Linux Professional Institute)が運営する国際資格です。
一方、LinuC(リナック)は、日本国内のLPI-Japanが独自に展開する資格体系です。
もともとは同じ内容でしたが、2018年以降に運営団体が分かれ、試験内容や方針が異なるようになりました。
LPICは海外でも通用し、グローバル企業や外資系での評価が高いのが特徴です。
対してLinuCは、国内IT企業での評価や実務対応力を重視しています。
Linux Essentialsはどんな人に向いている?
Linux Essentials(リナックスエッセンシャル)は、LPICの前段階にあたる入門資格です。
Linuxの基礎概念やオープンソースの考え方など、初心者向けの内容が中心です。
「これからIT業界を目指したい」「まずはLinuxを触ってみたい」という人にとって、
学習ハードルを下げる導入資格として最適です。
特に高校生・専門学校生・非エンジニア職からの転職希望者におすすめです。
LPICとLinuCはどっちがいい?選び方のポイント
どちらの資格も評価されますが、目的によって最適解が異なります。
- 国際的なスキル証明や外資企業を目指す → LPIC
- 国内転職・中小企業やSIerでの実務重視 → LinuC
- まずLinuxを基礎から理解したい → Linux Essentials
どちらが上位というわけではなく、どの環境で働きたいかで選ぶのが正解です。
将来的にクラウドやセキュリティ領域を目指すなら、LPICの方が継続的なスキルアップにつながります。
LPIC廃止の噂を正しく理解する3つの視点
「LPICって廃止されたの?」「もう受けられないって聞いたけど本当?」
SNSなどでこのような情報を目にした方もいるかもしれません。
ここでは、その“廃止の噂”を正しく理解するための3つのポイントを解説します。
LPIC廃止の誤解と背景
まず結論から言うと、LPICは廃止されていません。
一部のサイトやSNSで「LinuCができた=LPICがなくなった」と誤解されて広まっただけです。
背景として、2018年に日本のLPI-JapanがLPI本部(カナダ)から独立し、LinuCという独自資格体系を開始したことが原因です。
そのため、「国内での試験窓口が変わっただけ」であり、LPIC自体は今も世界中で認定・実施されています。
現在の試験運営・認定体制
現在、LPICはLPI本部が直接運営する国際資格として継続しています。
日本国内でも、ピアソンVUE経由で通常どおり受験可能です。
一方、LinuCはLPI-Japanが独自に運営しており、内容は似ていますが別資格です。
つまり、「LPIC=国際資格」「LinuC=日本独自資格」という整理が正確な理解です。
公式発表から見る今後の展望
LPI本部は公式サイトで、「LPICは世界標準のLinux認定資格として引き続き運営する」と明言しています。
そのため、LPICの廃止予定や停止に関する公式発表は一切ありません(2025年時点)。
むしろ、クラウドやDevOpsの普及により、Linux技術者の需要は世界的に増加しています。
LPICは今後も、国際的なスキル証明としての価値が続く資格といえるでしょう。
LPICの勉強法を成功させる3つのコツ(独学・スクール別)
「LPICの勉強、どこから始めればいいの?」「独学でも合格できる?」
そんな悩みを持つ方のために、ここでは独学とスクールそれぞれの勉強法を具体的に紹介します。
独学におすすめの教材・学習サイト
独学でLPICを目指す場合は、公式テキスト+オンライン問題集の組み合わせが最も効率的です。
おすすめ教材例:
- 『Linux教科書 LPICレベル1 Version 5.0対応』(翔泳社)
- Ping-t(オンライン問題演習サイト)
- Udemy(動画講座)
これらを活用し、1日2時間・3か月間を目安に学習すれば、未経験でも十分合格可能です。
また、学んだ内容を実際にLinux環境(VirtualBoxやWSL)で動かすと、理解が深まります。
スクールを利用するメリットと選び方
独学に不安がある方や短期間で確実に合格したい方は、スクールを利用するのも有効です。
スクールを選ぶ際は、以下のポイントを意識しましょう:
- LPIC対応カリキュラムがあるか
- 現役エンジニア講師が在籍しているか
- 模擬試験・質問サポートが充実しているか
たとえば「TechAcademy」や「SAMURAI ENGINEER」などでは、LPIC対応講座を提供しており、質問対応の手厚さが魅力です。
学習モチベーションを維持するコツ
LPICの学習は範囲が広く、途中で挫折しやすいのが難点です。
そこで効果的なのが、「学習の見える化」と「小さな成功体験の積み上げ」です。
- 学習時間をアプリで記録する(Studyplusなど)
- SNSで「#LPIC勉強中」と投稿してモチベ維持
- 1トピックごとに理解度をチェックする
特にモチベーションが下がったときは、「合格後のキャリア」や「転職後の年収アップ」をイメージすることで前向きに学習を続けられます。
LPICの有効期限と更新方法を理解する3つのポイント
「LPICって一度取れば一生使えるの?」「更新は必要なの?」
こうした疑問を持つ人も多いでしょう。LPICは資格更新制度があり、有効期限を正しく理解しておくことが大切です。
有効期限の仕組みと注意点
LPICの資格には、5年間の有効期限があります。
期限を過ぎると、資格ステータスは「Active(有効)」から「Inactive(失効)」に変わります。
ただし、失効しても資格が完全に消えるわけではありません。
履歴上は「取得済み」として残りますが、最新技術に対応していないとみなされる点に注意が必要です。
また、LPIC-1を持っていてLPIC-2に合格した場合、下位資格の有効期限も自動的に更新されます。
資格更新の方法と再認定条件
LPICの再認定を受けるには、同じレベルまたは上位レベルの試験に再度合格する必要があります。
たとえば:
- LPIC-1の有効期限が切れる前にLPIC-2に合格 → 自動的に更新
- LPIC-2を持っていて再受験する → 期限延長
この仕組みにより、最新の技術知識を維持しつつ、キャリアの継続的な成長をサポートできます。
更新を見据えたキャリア設計
LPICは更新制度がある分、「資格を取りっぱなしにしない」姿勢が求められます。
そのため、定期的に新しい技術(クラウド、セキュリティ、DevOpsなど)を学び、資格更新を成長のチャンスとして活用するのがおすすめです。
資格更新をキャリアマイルストーンとして設定すれば、モチベーション維持にもつながります。
LPIC取得後に伸ばすべき3つのスキルと次の資格
「LPICに合格したけど、次は何を学べばいい?」「この資格をどう活かせばいいの?」
そんな疑問を持つ方に向けて、LPIC取得後に身につけるべきスキルと次に目指すべき資格を紹介します。
LPIC-2・LPIC-3へのステップアップ
まずは、LPIC-2やLPIC-3などの上位資格を目指すのが自然な流れです。
LPIC-2ではサーバー構築・ネットワーク設定・セキュリティ設定など、より実践的なスキルを問われます。
さらに、LPIC-3は「セキュリティ」「仮想化」「高可用性」などの分野に分かれており、
専門領域を深めたいエンジニアに最適です。
上位資格を取得することで、リーダー職や設計ポジションにも挑戦しやすくなります。
AWSやCCNAなどクラウド・ネットワーク資格との相性
LPICは、Linuxの知識を軸に他の技術分野へ発展しやすい資格です。
特に相性が良いのは以下の2つです:
- AWS認定資格:クラウド上でのLinuxサーバー構築・運用スキルを活かせる
- CCNA:ネットワーク構成や通信の仕組みを理解することで、より実践的なサーバー設計が可能
これらを並行して学ぶことで、クラウドインフラ全体を設計・運用できるエンジニアへと成長できます。
LPICを活かせるキャリアパスの例
LPIC取得後の主なキャリアパスは次の通りです:
- サーバー運用担当 → インフラエンジニア → クラウドエンジニア
- 社内SE → ITインフラ設計担当 → プロジェクトリーダー
- フリーランスエンジニアとして独立
特に、LPICとAWS・CCNAを組み合わせると、上流工程(設計・構築)やクラウド移行案件にも携われるようになります。
資格取得をゴールではなく、キャリア成長のスタートラインと考えるのが成功の秘訣です。
まとめ
LPICは、Linuxの知識とスキルを体系的に証明できる、世界的に評価の高い資格です。
特にIT未経験からインフラエンジニアを目指す人にとっては、最初の大きなステップとなるでしょう。
LPICを学ぶ過程で、サーバーの仕組みやネットワークの基本、システム運用の考え方が自然と身につきます。
そのため、資格を取得すること自体がキャリア形成の大きな助けとなり、自信と市場価値の両方を高めることができます。
また、LPIC取得後には、AWSやCCNAなどのクラウド・ネットワーク資格を組み合わせることで、
さらに幅広いキャリアに挑戦できるようになります。
資格を「取って終わり」にせず、次の学びや実務に活かす姿勢が、成長を加速させるカギです。
最初の一歩は小さくても構いません。
LPICの勉強を始めることで、あなたのキャリアの可能性は確実に広がっていきます。
「Linuxに強いエンジニア」への道は、今日の学習から始まります。
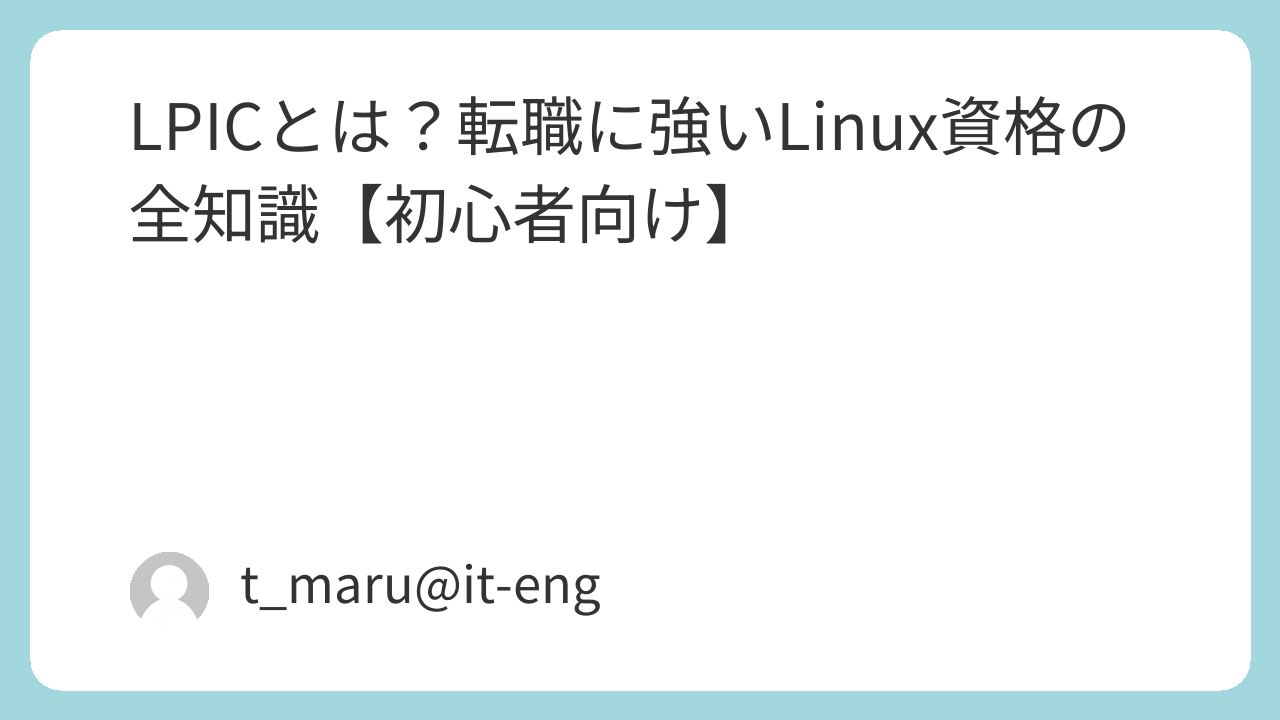
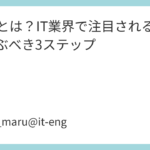
コメント