「CCNAの資格を取りたいけど、実際どれくらい勉強すればいいの?費用も気になるし、独学で本当に合格できるのかな…」
そう思う方もいるかもしれません。
実は、CCNAに合格するためには、200〜300時間の学習が目安とされており、ポイントを押さえれば社会人や初心者でも十分に合格可能です。費用についても、独学ならコストを抑えて学ぶ方法があります。
この記事では、CCNAに必要な勉強時間や費用の相場、効率的な学習スケジュール、無料で使える教材や演習ツール、申し込みの注意点まで、初めての人が押さえておくべき5つの重要ポイントを丁寧に解説していきます。
CCNAの勉強時間はどれくらい必要?【3つの目安で解説】
「CCNAってどれくらい勉強すればいいの?」と不安になりますよね。
本記事を読み進めれば、自分に合った勉強時間の目安が明確になります。
- 未経験者が合格するまでの平均勉強時間
- 学習期間の目安と1日の勉強時間のバランス
- CCNAの難易度と勉強時間の関係
まずは勉強時間の全体像から把握しましょう。
未経験者が合格するまでの平均勉強時間
CCNAを初めて受験する人が最も気になるのが「合格に必要な勉強時間」です。IT業界未経験者の場合、合格までに必要な勉強時間はおよそ200〜300時間とされています。これは、週15〜20時間の学習でおよそ3〜5ヶ月ほどかかる計算です。
ただし、この数字はあくまで目安であり、個人の理解度や学習スタイルによって変動します。たとえば、ITに親しみがある人や、すでにネットワークの基礎知識を持っている人は150時間前後でも合格するケースがあります。一方で、ネットワーク用語も初めて聞くというレベルからのスタートであれば、300時間以上必要になることも想定しておいた方がよいでしょう。
学習期間の目安と1日の勉強時間のバランス
実際に勉強時間を確保する上で大切なのは、「1日どれくらい学習に充てられるか」です。たとえば、平日に1日1時間、週末に2〜3時間のペースを守れば、3〜4ヶ月で合格ラインに到達することができます。逆に、短期集中で取り組みたい場合は、毎日2〜3時間の勉強時間を確保すれば、1〜2ヶ月での合格も現実的です。
ただし、長時間学習を詰め込むよりも、毎日少しずつでも継続することのほうが理解の定着には効果的です。CCNAは「暗記」よりも「理解」が問われる試験なので、詰め込み型よりも反復学習や実践演習を混ぜながら進める学習法が合格のカギとなります。
CCNAの難易度と勉強時間の関係
CCNAは初心者でも挑戦できる資格として人気がありますが、試験範囲は意外と広く、簡単に合格できる試験ではありません。特に未経験者にとっては、初めて耳にするネットワーク用語や構成の理解に時間がかかるため、勉強時間が長くなりがちです。
また、CCNAは一夜漬けでなんとかなるタイプの資格試験ではありません。合格には概念の理解 + 問題演習 + ラボ演習の3つをバランスよく行うことが求められます。
そのため、CCNAの難易度を正しく理解し、自分の現状に合わせたリアルな学習計画を立てることが重要です。焦って短期間で詰め込もうとせず、まずは一歩ずつ積み上げることが、最終的に合格への近道になります。
忙しい社会人がCCNAに合格するための3つのスケジュール例
「仕事が忙しくて勉強時間が取れない…」と感じていませんか?
この記事を読めば、限られた時間でもCCNA合格を目指せる学習スケジュールが見つかります。
- 1日1時間・3ヶ月で合格を目指すプラン
- 朝活やスキマ時間を活用した学習パターン
- 実際に合格した人のスケジュール例紹介
自分に合った学習スタイルを見つけてみましょう。
1日1時間・3ヶ月で合格を目指すプラン
忙しい社会人でも継続しやすいのが、**「1日1時間」×「3ヶ月」**の学習スタイルです。このペースなら無理なく習慣化でき、合計約90時間の勉強時間を確保できます。これに週末の追加学習(1日2〜3時間)を加えれば、3ヶ月で200時間前後の学習時間を確保することが可能です。
平日は通勤前の1時間や、帰宅後の時間を利用して理論学習。週末は時間を確保して、模擬試験や演習問題に集中するというスタイルが効果的です。毎日短い時間でも継続することが、記憶の定着とモチベーション維持につながります。
朝活やスキマ時間を活用した学習パターン
仕事が不規則な人や子育て中の方におすすめなのが、スキマ時間を活用する学習パターンです。たとえば、朝の通勤中にCCNAの解説動画を視聴したり、昼休みに参考書を読むなど、細切れの時間を積み上げるスタイルです。
また、夜のまとまった時間を「復習の時間」として活用すれば、インプットとアウトプットのバランスも取れます。スマホで使える学習アプリや音声教材を活用すれば、手を動かせない状況でも学習が可能になるのがこのスタイルのメリットです。
実際に合格した人のスケジュール例紹介
実際に合格した人のスケジュールを参考にすることで、自分の計画に現実味を持たせることができます。ある30代の社会人は、平日1時間+週末2〜3時間のペースで4ヶ月学習し、合格しています。
別の例では、シフト勤務のIT未経験者が**「週3日・2時間の集中学習」+「休日はラボ演習」**という形で、6ヶ月で合格を果たしたケースもあります。
大切なのは、誰かの学習法をそのまま真似ることではなく、自分のライフスタイルに合った計画を立てることです。日々の生活と無理なく両立できることが、長期的に学習を続けるカギとなります。
CCNAの勉強時間を効率化するための3つの工夫
「頑張って勉強してるのに、なかなか頭に入らない…」と感じたことはありませんか?
この記事を読めば、効率よく知識を定着させるための具体的な学習法がわかります。
- 学習範囲を絞って重点的に進める方法
- ラボ(演習)学習を取り入れて理解を深める
- モチベーションを保つための工夫
時間を無駄にしない工夫をチェックしてみましょう。
学習範囲を絞って重点的に進める方法
CCNAは試験範囲が広く、すべてを均等に学ぼうとすると時間が足りなくなります。特に未経験者の場合は、出題頻度の高い分野や自分が苦手な範囲に的を絞って学習することが効率化の第一歩です。
たとえば、IPアドレッシングやVLAN、ルーティングといった頻出トピックは、重点的に時間を割くべき対象です。一方で、実務での理解が深まってからでも問題ない部分は、初期段階では深追いしないのもひとつの戦略です。
試験対策本や公式ガイドをもとに「出るところ」と「出にくいところ」を見極めることで、限られた時間を効果的に使うことができます。
ラボ(演習)学習を取り入れて理解を深める
CCNAでは、「知識を覚える」だけではなく、「ネットワークを自分で組み立てられるか」が試されます。そのため、実際に手を動かして学べるラボ演習は非常に重要です。
Ciscoが提供する無料ツール「Packet Tracer」や、他のネットワークシミュレータを使えば、自宅でも仮想環境で設定作業を練習できます。紙の上だけでは理解しにくい内容も、目で見て確認しながら操作することで、知識が確実に身につきます。
「理論学習+演習」のセットで進めることで、試験本番でも慌てずに対応できるようになります。
モチベーションを保つための工夫
勉強の効率化において、忘れてはならないのが**学習を続ける「気持ちの管理」**です。特に長期戦になるCCNAでは、途中で挫折してしまう人も少なくありません。
モチベーション維持には、「小さな目標を立ててこまめに達成する」「学習記録をつけて自分の成長を見える化する」「SNSや学習コミュニティで仲間とつながる」といった工夫が効果的です。
また、参考書を変えて気分をリフレッシュしたり、勉強する時間帯や場所を少し変えるだけでも、気持ちが切り替わって集中力が戻ることもあります。心のコンディションを整えることが、結果的に勉強の効率アップに直結します。
CCNA合格に向けたおすすめの学習ツールと教材3選
「どの教材を使えばいいのか分からない…」と悩んでいませんか?
この記事を読めば、目的に合わせた効果的な学習ツールを選べるようになります。
- 独学に使える無料・低コスト教材
- スマホでも学べる動画・音声コンテンツ
- 模擬試験や演習ツールの活用方法
効率よく学べる教材選びのヒントを押さえましょう。
独学に使える無料・低コスト教材
CCNAの勉強は、スクールに通わなくても独学で合格を目指せるだけの教材が揃っているのが特徴です。中でもおすすめは、ネット上で手に入る無料教材や、数千円で購入できる公式テキスト・問題集です。
たとえば、Cisco公式の学習プラットフォーム「Cisco Networking Academy」では、基礎から学べる無料コースが提供されています。また、書籍としては「徹底攻略CCNA教科書」「CCNAイージーシリーズ」などが定番です。
これらの教材は、未経験者でもステップを追って理解できる構成になっており、費用を抑えながらもしっかりと力がつく点が魅力です。
スマホでも学べる動画・音声コンテンツ
通勤中や家事の合間など、スキマ時間を活用するには、スマホで学べる教材が便利です。YouTubeには、CCNA対策の解説動画を無料で配信しているチャンネルが複数存在しており、図解やアニメーション付きでわかりやすい内容になっています。
たとえば、「NetworkChuck」「Jeremy’s IT Lab」などは、海外の人気チャンネルで、実際の設定操作も視覚的に理解できます。さらに、音声だけで学べるPodcastやラジオ形式の講義もあり、目を使えない場面でもインプットが可能です。
動画学習は理解が早まり、繰り返し視聴することで記憶の定着にも効果があります。
模擬試験や演習ツールの活用方法
本番試験の形式に慣れるためには、模擬試験の活用が欠かせません。市販の問題集やオンラインの模試サービスを使えば、出題傾向を把握しながら弱点を見つけることができます。
また、CiscoのPacket TracerやBoson ExSimなどの演習ツールを使えば、実践的な問題を通じて「手を動かす学習」が可能です。こうしたツールを取り入れることで、ただ読むだけの学習から、実践力を身につける段階へと進めます。
試験直前には、模試→復習→再模試というサイクルを繰り返すことで、自信を持って本番に挑めるようになります。
初心者向けのわかりやすい参考書3選
CCNAの学習を始めたばかりの方には、図や図解が多く、専門用語を丁寧に解説している参考書がおすすめです。特に以下の3冊は、初心者から高い評価を得ている定番書籍です。
- 『徹底攻略CCNA教科書』
試験範囲に対応した構成で、図解が豊富。試験直前の総復習にも使える1冊です。 - 『1週間でCCNAの基礎が学べる本』
ざっくりと全体をつかみたい人向け。短期間で基礎を押さえたいときに最適です。 - 『よくわかるCCNAネットワーク入門編』
実務経験ゼロでも安心。会話形式で進むので、ネットワークのイメージが掴みやすいのが特徴です。
これらはいずれも未経験者のつまずきやすいポイントを丁寧にフォローしてくれる設計になっているため、初めて学ぶ方にも無理なく取り組めます。
紙の本と電子書籍、どっちがいい?
参考書の形式で迷う方も多いですが、それぞれにメリットがあります。
紙の本は、付箋を貼ったり、書き込みをしたりしやすいため、手を動かしながら覚える人に向いています。対して電子書籍は、通勤・通学中などの移動時間にも気軽に読めるうえ、持ち運びが便利です。
また、電子書籍であっても最近はマーカー機能やノート機能が充実しているため、スマホ一台で効率的に学習が進められる環境が整いつつあります。
目的別に選ぶ参考書の選び方
自分に合った参考書を選ぶためには、「今の自分にとって何が必要か」を明確にすることが大切です。
- ネットワークの基本から学びたい人 → やさしい解説中心の入門書
- 試験対策をしっかりしたい人 → 問題集付きの教科書タイプ
- 実践力を高めたい人 → 演習付きのテキスト+ラボ演習ガイド
このように、自分のゴールや課題を意識して選ぶことで、時間もお金も無駄にせず、効率的に学習を進めることができます。
過去問の活用法と試験対策の3つのコツ
「どんな問題が出るのか事前に知っておきたい…」と思ったことはありませんか?
この記事を読めば、過去問の入手方法から効果的な活用術まで分かります。
- CCNAの過去問はどこで手に入る?
- 過去問を使った効果的な復習方法
- よく出る問題の傾向と対策ポイント
試験対策を効率化するヒントを見ていきましょう。
CCNAの過去問はどこで手に入る?
CCNAには公式の「過去問集」が存在せず、試験内容も定期的に更新されるため、いわゆる“本物の過去問”は非公開とされています。ただし、それに近い内容を含む「予想問題」や「模擬試験」は複数の教材やWebサイトで提供されています。
特に人気なのが、**『徹底攻略CCNA問題集』や『CCNAイージー模試』**などの書籍。また、BosonのExSimや、MeasureUpといった海外サイトでは、実際の試験形式にかなり近い問題が多数収録されており、実践的なトレーニングが可能です。
過去問を使った効果的な復習方法
模擬問題や予想問題を活用する際は、「解いて終わり」にせず、間違えた箇所を徹底的に復習することが重要です。なぜその選択肢が正しくて、他が間違っているのか、ネットワークの仕組みに基づいて理解するようにしましょう。
また、**「1周目は全体をつかむ」「2周目で理解を深める」「3周目で定着を確認する」**という段階的な取り組み方が効果的です。記憶の定着と理解の深さを両立するためには、間を空けて繰り返し解く「分散学習」が有効です。
よく出る問題の傾向と対策ポイント
CCNAの試験では、特定のテーマが繰り返し出題される傾向があります。たとえば、IPアドレッシング(サブネット計算)・ルーティング・スイッチング・VLAN設定といった基礎項目は毎回のように登場します。
また、近年はセキュリティや自動化(Cisco DNA、SDN)などの新しいトピックも加わってきており、古い問題だけをやっているとカバーできない可能性もあります。
そのため、予想問題や模擬試験を活用しつつ、最新の出題傾向に対応した教材を選ぶことが、合格への近道となります。
CCNA試験の申し込み方法と受験料の確認ポイント【3ステップ】
「CCNAの試験って、どうやって申し込めばいいの?」という声をよく聞きます。
この記事を読めば、試験の申込手順や費用についての不安を解消できます。
- CCNAの試験申し込み手順を分かりやすく解説
- 試験費用はいくらかかる?最新の受験料をチェック
- 試験日程の選び方とキャンセル時の注意点
事前準備を整えてスムーズに受験に臨みましょう。
CCNAの試験申し込み手順を分かりやすく解説
CCNAの試験は、Ciscoが認定する試験機関である**Pearson VUE(ピアソンビュー)**を通じて受験予約を行います。手順は以下の通りです。
- Ciscoの公式アカウント(Cisco ID)を作成
- Pearson VUEのウェブサイトでアカウントを作成・ログイン
- 「試験検索」で「200-301(CCNA)」を選択
- 希望の会場・日時を選び、受験予約を完了
すべてオンラインで完結するため、忙しい社会人でもスムーズに申し込めます。申し込み時は、登録情報がパスポートや免許証などの本人確認書類と一致しているか必ず確認しておきましょう。
試験費用はいくらかかる?最新の受験料をチェック
2025年6月時点で、CCNA(試験コード:200-301)の受験料は**約33,000円(税込)**です。ただし、為替レートや試験会場の国・地域によって若干の変動があるため、申し込み時に表示される金額を必ず確認するようにしましょう。
また、再受験する場合も同額がかかるため、1回での合格を目指す人にとっては、しっかりと準備したうえでの受験が経済的にも安心です。企業によっては、資格取得の費用を補助してくれる制度がある場合もあるので、勤務先の制度も確認しておくと良いでしょう。
試験日程の選び方とキャンセル時の注意点
CCNAは通年受験が可能な試験で、全国のテストセンターまたはオンラインで受けることができます。自分の生活スケジュールに合わせて、無理のない日程を設定するのが理想的です。
なお、予約後に都合が合わなくなった場合は、試験日の24時間前までであれば無料で日程変更・キャンセルが可能です。それ以降の変更にはキャンセル料が発生する場合があるので、直前の予定変更には十分注意しましょう。
スケジュールを調整する際は、学習進度や模擬試験の結果をもとに、「この日なら自信を持って受けられる」と思える時期を選ぶのがベストです。
CCNAの試験日はいつ?スケジュール調整に役立つ3つの視点
「いつ試験を受けるのがベストなんだろう?」と迷っていませんか?
この記事を読めば、最適な試験日と学習スケジュールの組み立て方が分かります。
- 試験の実施タイミングと申し込み締切日
- 最短で受けるならいつがいい?
- 仕事や学校との兼ね合いを考えた日程調整
自分に合ったベストな試験日を見つけましょう。
試験の実施タイミングと申し込み締切日
CCNAの試験は、年に数回ではなく「いつでも受けられる」形式を採用しています。全国にあるPearson VUEのテストセンターや、自宅からのオンライン受験(OnVUE)を通じて、365日好きな日程で予約が可能です。
申し込みの締切日は、基本的に受験日の24時間前までとされていますが、土日や混み合う時期は希望日時が埋まってしまうこともあるため、余裕を持って1〜2週間前に予約するのがおすすめです。
最短で受けるならいつがいい?
最短で合格を目指すなら、まずは自分の勉強開始日から最低でも2〜3ヶ月先を目安に試験日を設定しましょう。これは、未経験者が必要とされる学習時間(200〜300時間)をもとに、毎日1〜2時間学習する場合の計算です。
また、「3ヶ月後の◯日」と試験日を先に決めてしまうと、逆算して計画が立てやすくなります。このような方法は「試験日ありきの逆算型スケジュール」と呼ばれ、モチベーションを維持しやすいスタイルとして多くの合格者に支持されています。
仕事や学校との兼ね合いを考えた日程調整
試験日は、自分の生活リズムや業務スケジュールに配慮して選ぶことが大切です。たとえば、業務が落ち着く月末や、連休の中日などを選べば、直前の復習時間も確保しやすく、余裕を持って受験に臨むことができます。
また、夜勤明けや体調を崩しやすい時期は避け、集中力が高まる時間帯(午前中など)を選ぶのもひとつの工夫です。試験前日には十分な睡眠をとり、当日は早めに試験会場に到着することで、安心して本番に臨めます。
CCNPとの違いとは?CCNAとの関係がわかる3つの比較ポイント
「CCNPってCCNAとどう違うの?どっちを取ればいいの?」と悩む人は多いです。
この記事を読めば、CCNAとCCNPの違いや関係性、学習の順番が明確になります。
- CCNAとCCNPの位置づけと違い
- CCNPを目指すならCCNAは必要?
- 初心者はどちらから始めるべきか
ネットワーク資格のステップを正しく理解しましょう。
CCNAとCCNPの位置づけと違い
CCNAとCCNPはどちらもCisco社が提供するネットワーク資格ですが、レベルや内容に明確な違いがあります。
**CCNA(Cisco Certified Network Associate)**はエントリーレベルの資格で、ネットワークの基本や運用・構築に関する基礎知識が問われます。一方、**CCNP(Cisco Certified Network Professional)**は中上級レベルの資格で、より専門的な設定・運用やトラブルシューティングに対応できるスキルを証明するものです。
つまり、CCNAはネットワークの土台を学ぶ資格、CCNPはその上に構築する専門資格と捉えると分かりやすいでしょう。
CCNPを目指すならCCNAは必要?
CCNPは、かつては「CCNA取得者であること」が受験の前提条件でしたが、現在はCCNAを取得していなくてもCCNPの受験が可能になっています。とはいえ、内容の難易度は段違いで、ネットワークの基本が分かっていないと太刀打ちできません。
そのため、多くの受験者はまずCCNAを取得してから、次のステップとしてCCNPに挑戦しています。公式教材やトレーニングもCCNAの理解を前提としているものが多いため、実質的にCCNA取得が推奨されていると考えていいでしょう。
初心者はどちらから始めるべきか
ネットワークやITの基礎知識がほとんどない初心者の場合は、迷わずCCNAから始めるのが正解です。CCNAの学習を通じて、IPアドレスやルーティングといったネットワークの基本構造を理解しておくことで、CCNPの学習もスムーズになります。
また、CCNAに合格することで自信がつき、次のステップへのモチベーションにもつながります。キャリア的にも、CCNAは未経験でインフラエンジニアを目指す際の登竜門的な位置づけにあるため、就職・転職の際にも役立つ資格です。
勉強時間をムダにしないための3つの注意点とコツ
「せっかく勉強しているのに、なかなか成果が出ない…」と感じることはありませんか?
この記事を読めば、学習効果を最大化するための工夫と注意点がわかります。
- 最初に学習の全体像をつかむ重要性
- よくある失敗とその回避法
- 本番直前の過ごし方と注意点
効率的な学習のための基本を見直しましょう。
最初に学習の全体像をつかむ重要性
CCNAの勉強を始める前に、全体の試験範囲と出題傾向をざっくり把握することが非常に重要です。何も知らずに学習を始めてしまうと、的外れな部分に時間をかけすぎたり、肝心な範囲が抜けてしまうことがあります。
まずは、Cisco公式サイトで試験の範囲を確認したり、信頼できるテキストや学習ガイドをパラパラと目を通して「どんな構成か」「自分は何がわからないか」を把握しましょう。これにより、学習の優先順位が明確になり、時間配分にも無駄がなくなります。
よくある失敗とその回避法
CCNAの学習における失敗で多いのは、「インプットだけで満足してしまうこと」と「計画がないまま進めてしまうこと」です。
知識を読む・見るだけで「分かったつもり」になると、本番の問題に対応できません。重要なのは、学んだ内容をアウトプット(問題演習・設定演習)で確認することです。また、計画を立てずにその場しのぎの勉強を続けてしまうと、やる気が切れて途中で挫折しやすくなります。
学習初期に**「週○時間」「○月に受験」といった目標を決めておくこと**で、迷いなく進めることができ、継続力にもつながります。
本番直前の過ごし方と注意点
試験直前は、焦って新しい知識を詰め込むよりも、今までの復習と弱点補強に集中するのがベストです。模擬試験で間違えた問題を見直し、基礎用語や手順を改めて確認しましょう。
また、前日は睡眠をしっかり取り、当日は早めに行動することも重要です。特にオンライン試験を受ける場合は、PCの設定やネット接続、本人確認の手順を事前に確認しておくことで、トラブルを防げます。
心身ともに万全な状態で試験に臨むことが、合格率を大きく左右します。最後まで気を抜かず、「いつも通り」の状態で問題に向き合える準備をしておきましょう。
まとめ:自分に合ったペースでCCNA合格を目指そう
CCNAの取得は、IT業界未経験の方でもしっかりと準備すれば十分に達成可能な資格です。必要な勉強時間の目安やスケジュールの立て方、効率的な学習法、参考書やツールの選び方などを知ることで、無理のない計画が立てられます。
特に忙しい社会人にとっては、毎日のスキマ時間や週末の使い方が勝負の分かれ目です。無理に詰め込むのではなく、自分の生活に合ったスタイルで、着実に学習を進めることが大切です。また、勉強の継続にはモチベーション維持も重要であり、自分なりのやりがいや進捗の見える化が支えになります。
この記事で紹介したように、CCNAの勉強は決して“根性論”ではなく、正しい方法と計画に基づけば効率よく合格に近づけるものです。焦らず、確実に力をつけながら、自信を持って試験に挑んでください。
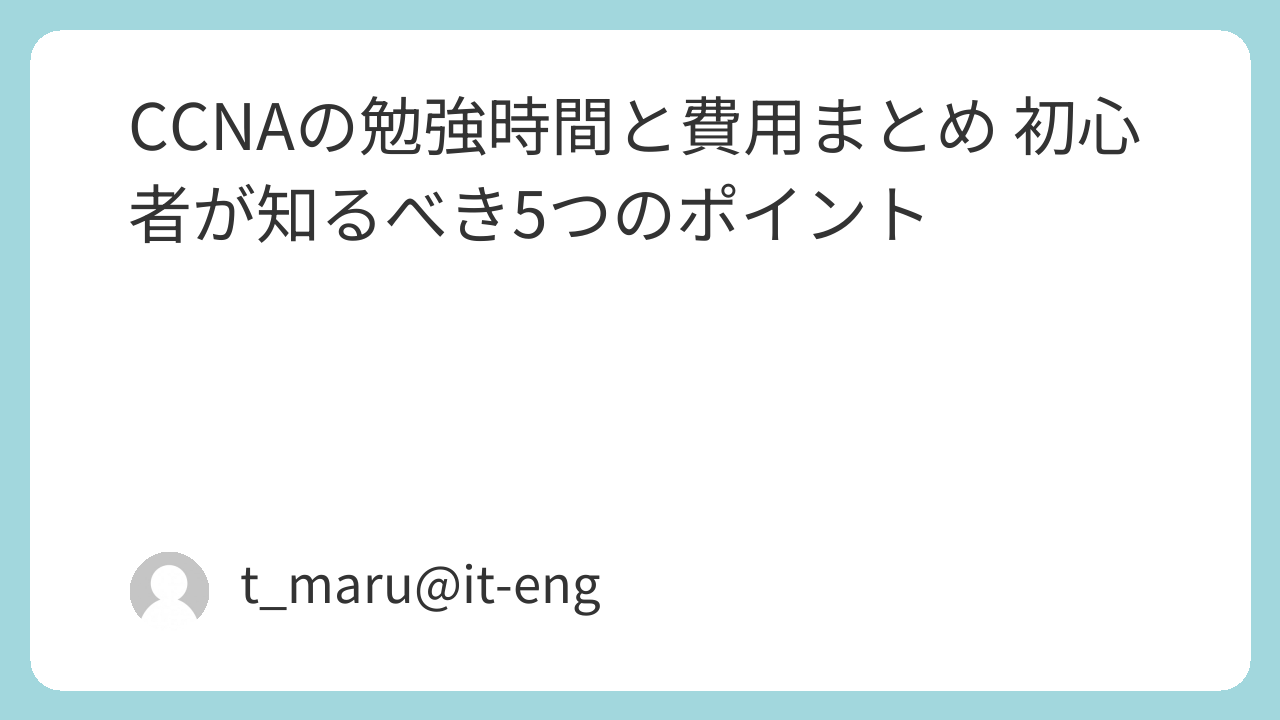
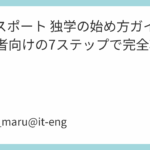
コメント